感動を生む
建築を。
Architecture that inspires.
Scroll
News

新着情報
2024.04.27
GW期間の学校休校に関するお知らせ

新着情報
2024.04.26
2024-25 OPEN CAMPUS
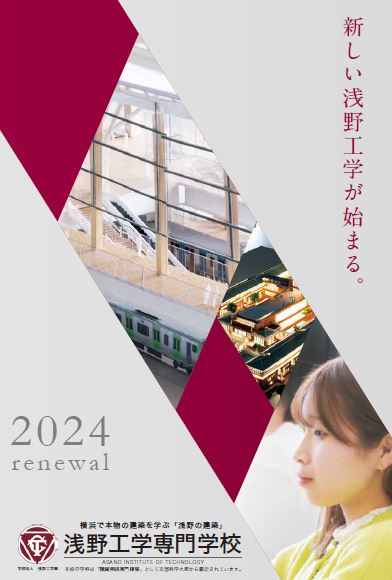
新着情報
2024.01.18
2024年度から学科名が変更になります
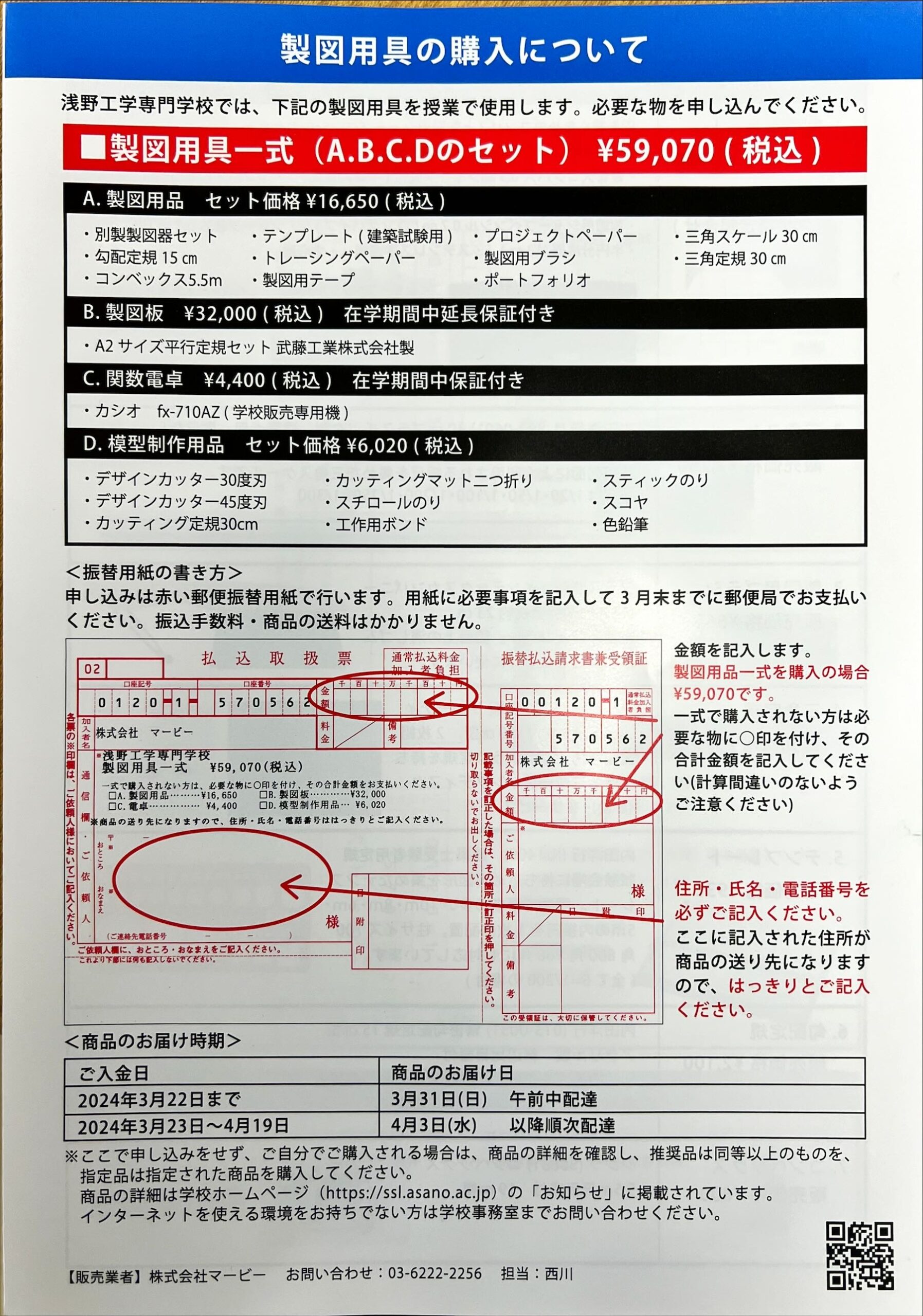
新着情報
2023.12.21
2024年度に入学される方への製図道具のご案内
Guidance
学校案内
建築家は、
人生の演出家でもある。
そこに集う人の、夢・希望・未来を彩る
Strengths
の特色
Introduction
学科紹介
学校生活
For Personal
受験生・保護者の方へ












